自治体版ウッドスタート

自治体版ウッドスタートの要綱・概要
現在、誕生祝品事業のご契約から配布まで、2年計画で進めております。
任意項目については、初年度か2年目に1つ目を実施、3年目以降は必要に応じて実施していただいております。
木育関係資料とは

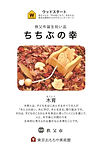
おもちゃのプレゼントだけで終わらないように、ウッドスタートの理念や木育についてわかりやすくまとめた書籍『赤ちゃんからはじめる木のある暮らし』を、おもちゃに添えて渡していただきます。“なぜ日本の木を使うのか”“なぜ木のおもちゃが良いのか”“木の特徴や効果”などをまとめています。また、自治体オリジナルの木製玩具の取扱説明やコンセプトをまとめた『しおり』も作成します。
誕生祝品事業の流れ
実地調査・製作業者訪問
初年度:ご契約~2カ月後頃
おもちゃのデザインを考案するために実地調査を行います。観光地だけではなく、象徴的な場所やモチーフとなる物など、地域性をデザインに取り入れます。製材所や木工所も見学し、地域材の調査や加工技術についても確認します。
デザイン画提供・製作者決定
初年度:実地調査~3カ月
2点のデザイン画を提供します。製作者の選定、及び、どちらか1点のデザインを採用をお決め頂きます。
※デザイナーによる“現物サンプル”の提供も可能です。(有償)
製作者による試作開始
初年度:デザイン決定~3カ月
製作者に、デザイン画に基づき試作を行っていただきます。デザイナーによるデザイン画は、作り方を細かく指定するものではありませんので、製作者ご自身で図面を起こしていただきます。
試作ブラッシュアップ
初年度:試作品提出~2カ月
製作者による試作品を、デザイナーと東京おもちゃ美術館で確認し、安全性の指針に基いてブラッシュアップを行います。仕様の変更が必要な場合は、ここで調整を行い最終仕様の確定を行います。
本製作開始
2年目:製作者、個数により変動
確定した最終仕様に基づき、納期を確定、製作者へ発注をします。
※令和2年度より、発注は基本的に自治体から製業者へ直接行っていただきます。
しおり作成
2年目:贈呈式から2カ月前
製品の取り扱い説明を含めたしおりを作成し、デザインの意図やおもちゃが出来るまでのストーリーを盛り込みます。
※写真の提供等、自治体・製作者にもご協力いただきます。
製品検品
2年目:贈呈式から1カ月前
自治体へ納品する前に数量のチェックや仕上がりを確認するため、東京おもちゃ美術館が検品を行います。
※令和2年度より検品は任意項目となり、必須ではなくなります。
贈呈式・ウッドスタート宣言
2年目:ご希望の時期
初回の贈呈式は大々的にセレモニーを行います。その場で、ウッドスタート宣言の調印式も行い、首長から代表の方におもちゃを手渡ししていただきます。
※配布までに必要な費用の概算です。配布目標時期に合わせたスケジュールのご提案をいたします。
詳細はお問合せ・ご相談ください。






